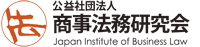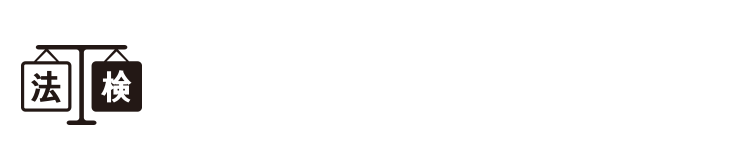法学一般 憲法 民法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法 商法 行政法 基本法総合〔民法〕
【法学一般】
問3
日本の立法過程に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.国会に提出される法律案は、誰が提出するかに応じて、議員提出法案、内閣提出法案、市民提出法案に分けられる。
2.各議院は、全議員からなる本会議での法律案の審議に先立って、原則として、議長が付託した委員会において実質的な審議を行う仕組みをとっている。
3.法律案の審議については、衆議院を先議院とし、参議院を後議院とする旨が、法により定められている。
4.提出権者別にみるならば、成立した法律の多くを占めるのは、議員提出法案である。
正解:2
〔講評〕
本問は、日本の立法過程に関する問題です。法律案等の議案が提出されたときは、議長はこれを適当な委員会に付託し、その審査を経て本会議に付す(ただし、とくに緊急を要するものは、議院の議決で委員会の審査を省略できる)(国会56条2項)ことになっており、正解は肢2です。肢1にいう「市民提出法案」なるものは日本の立法制度にはなく、肢3にいうような定めは法に存在せず(法律案が参議院で先に審議されることもあります)、肢4のいうところとは異なり、成立した法律の多くを占めるのは内閣提出法案です。
問6
つぎの条文は、男女共同参画社会基本法の附則の一部である。下線部「この法律」が指すものとして、正しいものを1つ選びなさい。なお、以下の附則は一部省略してある。
男女共同参画社会基本法
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(第2条、第3条 略)
附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11 年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(一、二 略)
1.平成11年7月16日法律第102号
2.男女共同参画社会基本法
3.内閣法
4.内閣法の一部を改正する法律
正解:1
〔講評〕
本問は、一部改正法の附則の理解に関する問題です。附則には、新規制定された法令に置かれる制定附則と、法令の一部改正法に置かれる改正附則とがあります。本問では、最初の「附則」が制定附則であり、2番目の「附則(平成11年7月16日法律第102号)」が改正附則です。前者の制定附則が男女共同参画社会基本法に置かれているのに対し、後者の改正附則は、男女共同参画社会基本法自体にではなく、男女共同参画社会基本法の一部改正法をその一部として含む「平成11年法律第102号」に置かれています。したがって、下線部「この法律」は、「平成11年7月16日法律第102号」を指します。肢1が正解です。
【憲 法】
問6
集団行動の自由に関する以下の記述のうち、判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。
1.行列行進や公衆の集団示威運動は、本来国民の自由とするところではあるが、公共の秩序を保持し、または、公共の福祉が著しく侵されることを防止する目的であれば、一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制したとしても、憲法には違反しない。
2.公共の安全に対し明らかな差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは行列行進や公衆の集団示威運動を不許可とすることができる旨の規定を設けたとしても、これは直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限することにはならない。
3.集団行動による思想等の表現には一瞬にして暴徒と化す危険が存在することが群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかであるため、これに対して法と秩序を維持するのに必要かつ最小限度の措置を事前に講じたとしても、憲法には違反しない。
4.集団行動について許可制が採用されていたとしても、一定の要件に該当する場合のほかは許可が義務づけられ、不許可の場合が厳格に制限されているものについては、このような許可制はその実質において届出制と異なるところがない。
正解:1
〔講評〕
本問は、集団行動の自由に関する判例の理解を問うものでした。ただ、本問は、個々の判決における言い回しの詳細にまで理解が及んでいることを求めるものでしたので、その限りでは、やや発展的な水準の出題だったといえるのかもしれません。とはいえ、本問で素材とされていた諸判例は、いずれも憲法における代表的な重要判例です。それゆえ、本問の各肢で問われていた内容は十分な学習が求められるものばかりであったことには、留意されたいところです。
本問の正答は、肢1でした。正答率は13.9%にとどまりました。これに対して、多くの受験生は肢3または肢4を選択しており、その割合は合わせて76%強にも上りました。肢1では新潟県公安条例事件(最大判昭29・11・24刑集8・11・1866)が素材とされ、肢3および肢4は東京都公安条例事件(最大判昭35・7・20刑集14・9・1243)では素材とされていました。この両判決はセットで学習し、両者を対比的に学ぶことが求められるものです。おそらくは、この対比が不十分であった人の多くが、本問で誤答してしまったのではないでしょうか。このようなことが今回の結果からは推察されます。
以下、具体的に解説すると、まず、肢1で問われていたのは、新潟県公安条例事件における次の説示についての理解でした。すなわち、「行列行進又は公衆の集団示威運動……は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり、本来国民の自由とするところであるから、条例においてこれらの行動につき単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されない」との言及についての理解です。とりわけデモ行進に関する「一般的な許可制」が憲法上許されない旨を指摘している箇所は、この判決において最も注目されるべきポイントです。それゆえ、この点について理解さえできていれば、肢1が「一般的な許可制」を違憲と解している箇所を「誤り」と判断することは、容易だったように思われます(換言すれば、それ以外の肢の正誤がまったく明らかでなかったとしても、上記の基本的な理解さえ備えていれば本問は正答できた問題といえるでしょう)。
他方、肢3と肢4では、東京都公安条例事件判決についての理解が問われていました。同判決については、代表的な判例集である『憲法判例百選Ⅰ(第7版)』ではAppendixでしか扱われておらず、その限りで学習が手薄になりがちという面があったのかもしれません。しかし、肢3で説かれていたような「集団暴徒化論」は同判決の最重要の説示であり、教科書や基本書でも十分に解説されているのが一般的です。「集団暴徒化論」を学習したことがあれば、肢3が「誤り」ではないことは明らかだったのではないでしょうか。その意味では、誤答してしまった受験生には、是非とも復習を促したいと思います。
とはいえ、両判決を通覧した場合、新潟県公安条例事件は「一般的な許可制」が憲法に違反する旨を判示し、デモ行進の事前規制について極めて消極的な態度を示している一方で、東京都公安条例事件では、集団暴徒化論を梃子にして、「不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない」と述べて、事前規制をも許容する姿勢を前面に出している点に関しては、判例の整合性という面で理解の難しさがあるのも事実です。しかし、東京都公安条例事件における最高裁の立場は、あらゆる事前規制を肯定したものでもなければ、「一般的な許可制」を許容したものでもありません。また、当然ながら、新潟県公安条例事件判決を判例変更したものでもありません。この点を注意深く確認しておくことは、東京都公安条例事件判決の理解においては大切だと思われますので、復習する際には十分気をつけましょう。
肢4では、許可制や届出制という概念に拘泥しない最高裁の姿勢についての理解が問われていました。東京都公安条例事件において、最高裁判所は、許可が義務づけられており、不許可の場合が厳格に制限されている場合には、規定の文面上で許可制を採用していたとしても、「この許可制はその実質において届出制とことなるところがない」と述べて、「集団行動の条件が許可であれ届出であれ、要はそれによつて表現の自由が不当に制限されることにならなければ差支えない」と判示していました。この説示も東京都公安条例事件判決の重要な特徴の1つですので、十分な復習が求められるところです。
このように東京都公安条例事件判決は、デモ行進の自由の制限に関する最高裁の立場を知るうえで少なくない情報を提供するものです。ですので、より詳しく理解したい場合には、これを機に、判決全文に触れて学習してみるのも悪くないように思われます。
【民 法】
2024年度法学検定スタンダード<中級>コース必須科目の民法について、正答率が1番低かった問題5と、2番目に低かった問題13(いずれも問題集には載っていない問題)を取り上げて講評します。
問5
Aは、Bとの有償の取引行為によって不動産(甲)の占有を開始した。その後、甲の所有者はCであることが判明したため、AはCに甲を返還した。この場合に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.Aが善意の自主占有者であったときは、Aは、甲から生じた果実をCに返還する必要はない。
2.Aが善意の他主占有者であったときは、Aは、甲から生じた果実をCに返還する必要はない。
3.Aが善意の自主占有者であった場合において、Aの故意によって甲が損傷していたときは、Aは、Cに対して損害の全部を賠償しなければならない。
4.Aが善意の他主占有者であった場合において、Aの故意によって甲が損傷していたときは、Aは、Cに対して損害の全部を賠償しなければならない。
正解:3
〔講評〕
選択肢1と2は、民法189条1項「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する」のとおりに、正しい内容を述べています(条文が自主占有者=所有の意思をもって占有する者と他主占有者=所有の意思のない占有者を区別していないことに注目してください)。物を買った(自主占有)にしろ、借りた(他主占有)にしろ、自分が有効な占有権原をもっていると信じて物を使用して果実を収取していたところ、実は契約が無効であるなどの理由で占有権原がなかったことが後から判明すると果実を返還しなければならないということになると、占有者は、そうした事態をおそれて物を使用することができなくなってしまうため、善意占有者の保護が規定されています。
また、選択肢4は、民法191条ただし書「ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない」のとおりに、正しい内容を述べています。これは、所有の意思のない占有者=他主占有者は、自分が占有しているのは他人の物であることを前提としている以上、それを故意・過失によって滅失・損傷させたときには、損害賠償責任を負うというルールを定めたものです。
選択肢3は、191条本文が「占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、……善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う」と定めていることに反しており、誤りということになります。ここでは、占有者は、自己の物だと信じて占有しているので、その信頼を保護するため、故意・過失でその物を滅失・損傷させたとしても、損害の全部を賠償する責任を負わない(利得が残る限りでそれを賠償させる)ことが定められています。
以上のことは、条文として覚えていなくても、売買(自主占有原因)や賃貸借(他主占有原因)に基づく占有を想定し、原因となる契約が無効であったがそのことについて善意であったという具体的なケースをイメージすれば、当事者の利益の衡量から解答にいたることができると思います(ややマイナーな条文ながら、正答率がそこまで低くなかったことからは、こうした利益衡量ができた受験生が相当数いたことがうかがえます)。普段の学習から、条文をそのようなイメージに結びつけて身につけることが重要です。
問13
AB間の双務契約から生じたAの金銭債務(甲)とBの債務(乙)は、同時履行の関係にある。Aは履行期に甲を履行しておらず、Bは乙の履行の提供をしていない。この場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。
1.BがAに対して甲の履行を求める訴えを提起した場合において、Aが同時履行の抗弁を主張したときは、引換給付判決がされる。
2.BはAに対して、甲の不履行を理由とする損害賠償請求をすることができない。
3.Bは、甲の不履行を理由とする契約の解除をすることができない。
4.Bは、甲・乙とは別の発生原因に基づく金銭債務(丙)をAに対して負っている。この場合、Bは、甲と丙を相殺することができる。
正解:4
〔講評〕
乙債務の履行の提供がされていないことから、Aは、同時履行の抗弁によって甲債務の履行を拒むことができる状況です。選択肢1から3は、こうした状況における基本的な効力を説明したものであり、いずれも正しいことを述べています。
これに対して選択肢4は、同時履行関係に立つ甲乙間ではなく、それとは別の丙との間の相殺が問題になっていますが、乙の履行提供がされないままに甲の履行が強制されたのと同じような結果になることを防ぐという趣旨から、このような相殺は許されないものと解されています(大判昭13・3・1民集17・318)。したがって、誤ったことを述べていることとなり、この選択肢を選び取ることになります。
選択肢4は、やや応用的な解釈を含む問題であり、難しい問題と感じた人も多かったかもしれませんが、選択肢1から3が同時履行の抗弁についての基本的な効力であることからすると、これらの選択肢を選ぶという誤答がやや多かった(特に選択肢3を選んだ受験生が3割近くいた)ことは、少し残念な結果であったと感じます。条文の知識を身につける際には、具体的な帰結まで落とし込んで理解することが必要です。
【刑 法】
問6
違法性の意識に関する各見解についての以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア説:故意の成立のためには、違法性の意識が必要である。
イ説:故意の成立のためには、違法性の意識の可能性が必要である。
ウ説:違法性の意識の可能性は、故意とは別個の責任要素である。
エ説:違法性の意識も違法性の意識の可能性も犯罪の成立要件ではない。
1.ア説によれば、刑法38条3項のただし書は、違法性の意識はあるが、刑罰法規を知らない場合について、刑を減軽しうる趣旨を定めた規定だということになる。
2.イ説によれば、違法性の意識を欠いたことにつき相当な理由がある場合、故意は阻却される。
3.ウ説によれば、刑法38条3項の本文は、刑罰法規を知らなくとも故意は成立する趣旨を明らかにしたものであると解釈されている。
4.エ説は、判例が伝統的にとってきた立場である。
〔参照条文〕刑法
(故意)
第38条 1・2(略)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
正解:3
〔講評〕
本問は、違法性の意識に関する問題であり、判例・裁判例のおおまかな流れ、刑法38条3項の解釈をめぐる議論について、基本的な理解を問うものです。ア説は厳格故意説、イ説は制限故意説、ウ説は責任説、エ説は違法性の意識不要説とよばれている見解です。約40%の受験者が肢4を選びましたが、判例の主流は、大審院の時代から、エ説(違法性の意識不要説)に立っています。たしかに、戦後の下級審裁判例においては、イ説(制限故意説)に立つものも少なからずみられ、比較的新しい最高裁判例は、再検討も示唆してはいます。しかし、最高裁は、なお、戦前から採用してきたエ説の枠組みを明確には変更していません(最決昭62・7・16刑集41・5・237)。また、17%ほどの受験者が肢2を選びましたが、この記述は、イ説(制限故意説)の内容を素直に表現したものです。
約25%の受験者が肢1を選びました。ア説(厳格故意説)はエ説(違法性の意識不要説)の対極に位置する見解ですが、この説をとった場合、38条3項ただし書について、肢1のように帰結すると理解されています。正解の肢3は、ウ説(責任説)に関するものですが、この見解は、38条3項本文を単なる法規の不知に関する規定ではなく、違法性の錯誤は故意の成立とは無関係であることを定めた規定であると解釈しています。したがって、肢3は誤りであるということになります。
【民事訴訟法】
問4
訴訟能力に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.未成年者が訴訟行為をするためには、法定代理人の同意が必要である。
2.一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関する訴訟において、法定代理人によらずに訴訟行為をすることができる。
3.被保佐人が保佐人の同意なしにした訴訟行為は、取り消すことができる。
4.被保佐人が、相手方の提起した訴えについて訴訟行為をするためには、保佐人の同意を要する。
正解:2
〔講評〕
本問は当事者の訴訟能力に関する基礎的な知識を問うものですが、正答率はかなり低い結果となりました。民事訴訟法が定める訴訟能力は民法が定める行為能力に対応する制度です(民訴28条)。しかし、両者の規律には訴訟手続の特性に基づく大きな違いがあり、この違いを理解することが、民法とは異なる考え方に立つ民事訴訟法を正しく理解するための第1歩となります。また、選択肢1、3、4にある「訴訟行為」は「法律行為」と同じ概念ではありません。この点を誤解している方が多かったようです。改めて教科書の該当箇所をチェックしてください。
問14
判決の種類に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.裁判所は、同一訴訟手続によって審判される事件の一部について、他と切り離して終局判決をすることはできない。
2.中間確認の訴えに対する判決は、中間判決である。
3.訴え却下判決は、終局判決である。
4.1000万円の金銭債権のうち100万円を請求する訴訟において、この請求を全部認容する判決は、一部認容判決である。
正解:3
〔講評〕
本問は、判決の種類に関する基礎的な知識を問うものですが、正答率はかなり低い結果となりました。正解できなかった方は、選択肢1または4の記述を正しいと判断したようです。しかし、終局判決の1種である一部判決をすることは法律上禁止されていませんから(民訴243条1・2項参照)、1は誤りです。また4は、請求額を限定した一部請求の訴えを全部認容する判決のことを説明しています。したがって、4の記述が一部認容(一部棄却)判決の説明であるはずがありません。この機会に、終局判決と中間判決、本案判決と訴え却下判決(訴訟判決)、全部認容判決と一部認容判決の区別を教科書で確認しておいてください。
【刑事訴訟法】
問11
Xは、Aを包丁で刺殺したとする殺人の罪で起訴された。この事件で裁判所が採用した証拠に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。ただし、選択肢1~3の証拠は、立証趣旨を「本件の犯人がXであること」として検察官がその取調べを請求したものとする。また、選択肢4の証拠は、本件の目撃者とされるBの証人尋問が終了した後に、立証趣旨を「Bの目撃証言が信用できないこと」としてXの弁護人がその取調べを請求したものとする。
1.Xの指紋とAの血痕が付着した包丁は、直接証拠である。
2.XがAを包丁で刺しているところを目撃した旨のBの証言は、直接証拠である。
3.Xが犯行時刻直前に犯行現場付近の金物屋において本件で使用されたのと同じ型の包丁を購入していることを示す領収書は、間接証拠である。
4.Bの裸眼視力が0.2であることを示す視力診断書や、本件犯行を目撃した際にBが眼鏡をかけておらずコンタクトレンズも入れていなかったと思われる旨のBの知人Cの供述を録取した書面は、補助証拠のうちの弾劾証拠である。
正解:1
〔講評〕
この問題は、証拠の分類のために用いられる概念(実質証拠と補助証拠、直接証拠と間接証拠、弾劾証拠と増強証拠、回復証拠)についての理解を問うもの(新作)です。
本問では、正答率が14.1%にとどまり、刑事訴訟法の出題の中で誤答が目立つ結果となりました。
まず、証拠の分類に際し、その証拠により証明しようとする事実の性質やその証拠のもつ機能に着目し、①最終的に証明すべき犯罪事実(要証事実)の存否の証明に用いられる「実質証拠」、証拠能力や証明力の判断に役立つ事実(補助事実)の証明に用いられる「補助証拠」、②「実質証拠」のうち、要証事実を直接に証明する証拠を「直接証拠」、その他の(間接事実を介して要証事実の立証に役立つ)証拠を「間接証拠」、③「補助証拠」のうち、実質証拠の証明力を減殺する事実を証明する証拠を「弾劾証拠」、証明力を増強する事実を証明する証拠を「増強証拠」、いったん減殺された証明力を回復する証拠を「回復証拠」とよびます。
たとえば、直接証拠は、「要証事実を直接に証明する証拠」をいいますが、本問は、その直接証拠についての理解を、単なる定義についての知識にとどまらず、当該証拠が「要証事実を直接に証明する」とはどういうことか、について、簡単な設例を用い、具体的な推認過程を踏まえて判断することができるか、という形で問うものでした。
その意味では、発展的な出題であるようにみえますが、当該証拠によって直接推認することができるのがどのような事実であるかは、「証拠の関連性」の判断そのものですし、ある供述が伝聞証拠(刑訴320条1項)に該当するかも、その供述から要証事実を推認するにあたり、供述者の供述過程に問題がない(誤りのおそれが払拭されている)ことを前提とするか、という判断をともないますから、証拠から事実への推認過程についての理解は立証活動の基礎だといえ、推認過程を正確に分析する力は証拠法の分野を通じて求められることとなります。
設例において要証事実とされる、「XがAを包丁で刺殺した」ことを直接に証明する証拠の典型としては、自白や(肢2のような)目撃者の供述があげられるのが一般的です。これらは、被告人の犯行を内容とする供述であり、当該証拠から要証事実を(さらに何らかの事実を推認したり、付加したりすることなく)直接推認することができますので、直接証拠にあたります(したがって、肢2は正しいのですが、今回は、これを誤りとした受験者が47.2%に及んでおり、証拠の分類に用いられる概念についての理解が十分ではないことを窺わせる結果でした)。
これに対して、肢3の「領収書」から直接推認することができるのは、Xが犯行時刻直前に犯行現場付近の金物屋において本件で使用されたのと同じ型の包丁を購入した事実です。その事実から、Xが犯行時刻直前に犯行現場付近にいた事実に加え、犯行に使用されたのと同じ型の包丁を所持していた事実を推認することはできますが、その領収証の記載内容(が真実であったとしても、それ)からXが当該包丁を使用して本件犯行に及んだ事実を直接推認することはできません(例えば、Xが犯行時に犯行現場にいたことは、別の証拠で立証しなければなりません)ので、当該領収書は間接証拠です(肢3は正しい)。
続いて、肢1の「包丁」から直接推認することができるのは、当該包丁にXの指紋とAの血痕が付着している事実です。この事実から、Xがその包丁を手にした事実を推認することはできますが、いつ、どのようにしてXの指紋とAの血痕が付着したのか、その包丁自体からは分からない(たとえば、別人による犯行後、現場を通りかかったXが当該包丁に触ったのかもしれません)ため、Xがその包丁でAを刺した事実を直接推認することはできませんので、当該包丁は間接証拠です(肢1は誤り)。
最後に、肢4の、本件の目撃者とされるBの「視力診断書」や、「Bの知人Cの供述を録取した書面」は、Bの証人尋問が終了した後に、Xの弁護人が、立証趣旨を「Bの目撃証言が信用できないこと」としてその取調べを請求したものです。これらは、要証事実の存否ではなく、Bの目撃証言(=Xの犯行を直接に証明する実質証拠)の証明力に関する事実の証明に用いられる補助証拠であって、Bの供述の信用性を減殺する弾劾証拠にあたります(肢4は正しい)。
証拠法の議論は、証拠の分類に用いられる概念について理解していることを前提に行われます。この機会に、ここまで紹介した概念それぞれの定義、そして、実質証拠と補助証拠、直接証拠と間接証拠、弾劾証拠と増強証拠を区別する基準について、本問の設例を素材として確認していただきたいと思います。
2024年のスタンダードコース商法の問題について、相対的に皆さんの間違いが多かった問題として、問題7と問題9を取り上げて、講評を行いたい。両方とも、問題集にない新作であり、これまで問題集で出題されていたものと異なる切り口で問うたり、問題集で扱っていないテーマについて問たりしている。法学検定試験スタンダードコースは、問題集から7割程度の出題がされ、残りの3割程度は新作である。今回取り上げる新作は、いずれも、問題で別の切り口から問われるものを再構成したり、問題では問うていないが解説で説明をしたポイントを中心に問題を組み直したりしたものである。法学検定試験問題集は、それだけでも体系的な学習や知識確認に資するように構成されている。解説にも目を通し、単に問題で扱われる選択肢の正誤を「覚える」のではなく、それぞれの根拠などを踏まえて、理解してほしい。
以下、問題7と問題9について解説しよう。
問7
社債に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.社債の金額が社債を引き受ける者にとって特に有利な金額である場合、発行する社債の募集事項の決定は株主総会の特別決議によって行わなければならない。
2.社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
3.会社が社債を発行する場合において、社債管理者を定めないときは、必ず社債管理補助者を定めなければならない。
4.株式会社が社債権者に対して支払う社債に係る利息の金額の総額は、その支払をする日における分配可能額を超えてはならない。
正解:2
〔講評〕
この問題は、新作であるが、問題集問題43をアレンジしたものであり、一部選択肢が重複している。会社の資金調達として、株式を利用する場合との比較を通して、社債での資金調達の意義を明確にしようとする選択肢(1、4)と、制度確認をしようとする選択肢(2、3)とで構成される。正解の選択肢2を選べた受験生は全体の45.8%である。残りの誤りの選択肢のうち、正しいと誤解した選択肢は、1が相対的には多いが、それほど差がなく、3、4も選ばれており、どれが誤りの選択肢かという確信を受験生が持てていなかった可能性がある。制度確認をする選択肢は、いずれも、問題文の解説での説明がされたポイントである。
正しい選択肢の2は、新株予約権付社債の譲渡に関して問う問題41の選択肢1の解説で説明したポイントであり、株券が発行された株式と同様、社債券が発行された社債につき、社債券の占有をする者の権利者推定がされる(会社689条1項)。また誤った選択肢である3は、問題43の選択肢3の解説で説明したポイントである。社債の管理を巡っては、社債権者が自身で管理ができる場合(管理をするために社債権者間で関心を持って調整の行動がとれると考えられる場合)、すなわち、各社債の金額が1億円以上の場合や社債権者の数が50名を下回る場合でなければ、社債管理者を置かなければならない。しかし、社債の償還・利息支払の業務などについては発行会社に代わって作業を実施する者を置くことも合理であり、社債管理者を設置しなくてもよい場合に、任意で社債管理補助者を置くことも可能である(会社714条の2)。
このように、選択肢2、3の正誤は、問題集を解説まで目を通し学習をすれば、判別することができる。
選択肢1、4は、問題集問題43の選択肢1、2と同様である。この選択肢は、資金調達に関して会社法が提供する手段として、社債と募集株式の発行がある。募集株式発行は「株式」を資金調達に利用するものであり、株式が会社の社員権の割合的・均等な単位として存在し、「企業価値÷発行済株式総数」によりその価値が決定される構造があるため、募集株式の発行の発行価格が既存の株式の価値よりも低い場合には、既存株主から、募集株式の引受人に富の移転が生じる。既存株主の有する株式の価値は、企業価値÷株式発行前の発行済株式総数で算出され、募集株式の引受人の払込金額が、既存株式の価値より低い場合は、企業価値の増加分に比して発行済み株式総数の増加分が多く、株式の価値は株式発行前の株式価値より低下し、既存株主の有する株式の価値は低下する。しかし、募集株式の引受人の払った引受価額よりも株式発行後の株価は高く、その差額分募集株式の引受人は利得することになる。この状況を富の移転という。このため、募集株式発行にあって、株主割当ての形式をとらず、募集株式の発行のときの株価よりも有利な価額で発行される場合には、非公開会社では、募集株式発行の募集事項決定は株主総会の特別決議によるが(会社199条2項・309条2項5号)、有利発行となることの説明をしなければならず(会社法199条3項)、公開会社では、原則募集株式発行の募集事項の決定は取締役会決議で行うが、有利発行は株主総会の特別決議で決定しなければならない(会社201条1項・199条2項)。
社債は、会社から見れば借財にすぎず、会社の業務執行として、募集社債に関する事項は業務執行上の決定として取締役会等で決定できる(監査役設置会社〔会社362条4項〕)では取締役会決議事項であり、監査等委員会設置会社では原則取締役会決議事項であるが(会社399条の13第4項)、社外取締役が過半数であるか、定款授権により業務執行取締役に委任でき(同条5項参照)、指名委員会等設置会社では、執行役に委任できる〔会社416条4項〕)。社債は会社の債務であり、負債を増加させ、会社のデフォルトリスクを上昇させるという影響を与えるにせよ、取締役の業務執行の問題として、取締役の責任の問題として評価されれば足りることから、株主総会などが決定に関与することは想定されていない。
このほか、株式については平等取扱いが要求され、同一の種類の株式はその有する株式の数に応じて取扱いをしなければならない(会社法109条1項参照)。これに対して、社債は、事務手続の煩雑さを減少させるために一回の発行で発行される社債については条件を同一化させる要請がはたらくにせよ、社債間は平等に取り扱われなくてもよい。同一の発行手続で実施されるものでなければ、既発行の社債と新たに発行される社債との間で同一条件とする要請はない。逆に発行時期が異なっても、利率、償還方法・期限などが同一のものであれば同じ種類と設定することもできる(会社681条1号、会社則165条)。このため、既発行の社債(種類の異なる社債)と条件が異なろうが何ら問題はない。以上から選択肢1は誤りである。
社債に対する利息の支払は、会社の費用としての支出であり、それについて制約はなく、利息の設定は私的自治の範疇(会社(取締役)と社債の引受人との交渉)で決定される(利息制限法の適用もない。最判令3・1・26民集75・1・1)。株式への配当が会社財産の株主への移転を意味し、会社債権者との調整が必要であり、分配規制(会社461条)があることとは異なる。したがって、選択肢4も間違いの選択肢である。
問9
監査役設置会社であるが、監査役会設置会社ではない取締役会設置会社において、必ずしも取締役会で決定する必要はなく、取締役に決定を委任できるものを、以下のうちから1つ選びなさい。なお、当該会社の定款に別段の定めはないものとし、見解が分かれている場合には最高裁判所の判例によるものとする。
1.支配人その他の重要な使用人の選任
2.代表取締役の解職
3.多額の借財
4.株主総会決議で定めた報酬総額の枠内での取締役の個人別の報酬の額の決定
正解:4
〔講評〕
問題9も新作であるが、問題集の問題57のアレンジであり、監査役設置会社の取締役会の決議事項のうち、取締役に委任できるものが何かを問うている。選択肢2、3は、問題集57と同様であるが、選択肢1、4は新たに設置したものであり、選択肢4は、問題領域が異なる報酬規制を扱い、必ずしもこれまで問題集で扱っていなかったポイントを聞いている。このため、問題9は受験者には難しかったかもしれず、正解の取締役(代表取締役)に委任できる事項である選択肢4を選ぶことができたものは4割に届かなかった。
この問題は大きく分けて2つの点を聞く。
第1は、取締役会が業務執行に関する決定のうち、取締役会が、その決議等により業務執行取締役に委任できることを問うものである。取締役会は、会社の業務執行に関する決定を行う機関である(会社362条2項1号)が、重要な業務執行上の決定(会社362条4項)と法令および定款により取締役会の権限と定められたもの以外の業務執行上の決定にを、取締役会決議(取締役会が定める規則を含む)等により、代表取締役・代表取締役以外の業務執行取締役、取締役で構成される任意の委員会(常務会など)に委任することができる。代表取締役の選定の取締役会決議には、代表取締役の日常業務に関する業務執行権限を付与することも内包されている(選定にともない当然に委任されている)と考えられる。選択肢1、2、3に関する決定はいずれも、会社法362条4項に列挙される重要な業務執行の決定であり、取締役会はそれを代表取締役等に委任することは認められていない(同条同項)。この点は、問題集問題57と条文や会社法の標準的なテキストで学習していれば、理解が可能である。
第2は、選択肢4に関する事項であり、監査役設置会社の取締役報酬規制の理解を問う。監査役設置会社の取締役の報酬については、定款または株主総会で「額」等を決定しなければならない(会社361条1項)。最判昭60・3・26判時1159・150にあるように、実務上は、定款で報酬の額を定めることが少なく、株主総会決議により取締役全員の報酬の総額の上限額を定め、その範囲内で個人別の報酬額を取締役会に授権する。
会社法が報酬の「額」を定款または株主総会で決定するとするのは、取締役によるお手盛りを防止することを目的とするためである。しかし、個人別の報酬額を株主総会で示すことはプライバシーの観点から問題もある。そこで、すべての取締役の報酬総額の上限額を株主総会で決定し、その範囲内で取締役会により個人別報酬額を決定しても、お手盛り防止をはかることができるとして、個人別の報酬額の決定を株主総会決議により取締役会に授権することも認められると理解した(取締役の会社に対する報酬請求権は、個人別報酬額が決定される取締役会決議時に発生する)。実務上は、株主総会より取締役会に授権された個人別報酬額の決定権限を、取締役会がその決議により代表取締役に一任することが多くあり、その点は、判例も肯定している(たとえば最判昭58・2・22判時1076・140など)。選択肢4は、この点を問う。
もっとも、取締役会が取締役の職務執行状況の監督機関であり、代表取締役の選定解職権限を有し、代表取締役の監督を行うことからは、監督対象の代表取締役が、取締役の個人別報酬額を決定できるとすることは不適切な影響を与える可能性がある。このため、公開会社でかつ大会社であり、発行する株式につき有価証券報告書を提出する監査役会設置会社は、株主総会決議で個人別の報酬等の額の決定を取締役会に授権する場合には、取締役会は個人別の報酬額の決定方針を定め(会社361条7項、会社則98条の5)、事業報告に開示しなければならないとされている(会社則121条6号。問題61の選択肢3の解説を参照)。個人別報酬額を取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が決定する場合には、その旨や決定者の氏名や会社内の地位・担当なども事業報告に記載する(同条6号の3)。
以上からは、選択肢4が正しい選択肢として、解答をしなければならないが、会社法361条7項の立法の経緯を踏まえれば、適切な対応とはいいにくいところがあり、正しい選択肢と自信をもって解答できなかったかもしれず、取締役の報酬規制の理解が完了していなければ、難しく感じたかもしれない。
問9
国家補償に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.判例によれば、公務員に故意重過失があるにもかかわらず国家賠償責任を免責する規定を特別法に設けることは、憲法17条に違反して無効となる可能性がある。
2.公務員の無過失による行為は国家賠償法1条の責任の対象とはならないが、特別法において、公務員の故意過失を問うことなく国に賠償責任を負わせる規定を設ける例がある。
3.判例によれば、国営空港の供用にともなって騒音被害が生じていれば、航空機の離発着について支障がない場合であっても国家賠償法2条の瑕疵が認められる余地がある。
4.判例によれば、行政財産の使用許可によって与えられた使用権は当該行政財産本来の用途または目的上の必要が生じた時点で消滅するから、その時点以降の当該使用権の撤回に際して使用権者に損失補償が認められる余地はない。
正解 4
〔講評〕
本問は、国家補償に関する最高裁判例および法律に関する知識を問うものです。記述内容に誤りがある肢を選ぶ問題であり、正解は肢4です。最判昭49・2・5民集28・1・1では、使用権者が行政財産の使用許可に関して対価を支払っており、その対価を償却するに足りないと認められる期間内に許可が撤回されるなどの場合には、例外的に使用権者に対する損失補償を認めうるとされています。したがって、肢4の内容は正しくありません。一方、最大判平14・9・11民集56・7・1439は、旧郵便法が定めていた書留郵便に係る故意重過失の場合の免責、特別送達に係る軽過失の場合の免責を憲法違反と判断しているので、肢1の内容は正しいと言えます。最大判昭56・12・16民集35・10・1369では、国営空港から発せられる騒音につき国家賠償法2条に基づく国家賠償が認められているので、肢3も正しいと言えます。国税徴収法112条1項では「換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。」と定められており、同条2項1文では「前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。」とされています。よって、肢2は正しい内容を記述しています。
申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分に対する審査請求が却下又は棄却された場合にも提起することができます。しかし、一定の裁決を求める義務付け訴訟は、原処分の取消しの訴えまたは無効等確認の訴えを提起できないときに限り、すなわち、裁決に対してのみ訴えの提起が認められる裁決主義が採用されているときに限り提起できます(行訴37条の3第7項)。肢4は、原処分の違法は原処分の取消訴訟等でのみ主張できるとする原処分主義(行訴10条2項)や裁決主義に関する理解も問われるため、若干高度であったと思いますが、この機会にあらためて申請型義務付け訴訟に関する条文について、復習してください。
【基本法総合〔民法〕】
2024年度法学検定スタンダード<中級>コース基本法総合の民法について、正答率が低かった問題5および問題6(いずれも問題集には載っていない問題)を取り上げて講評します。
問5以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして、正しいものを1つ選びなさい。
1.Aは、甲土地を所有し、自己名義の登記を備えていた。Bは、Aに無断で自己所有の土地として甲の占有を開始し、やがて取得時効が完成した。その後、Aは、Cとの間で、甲をCに売る旨の契約を締結し、Cへの所有権移転登記を済ませた。この場合において、Cは、Bに対して、甲の明渡しを請求することができない。
2.Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売る旨の契約を締結し、次いで、Cとの間で、AがCに対して負う貸金債務の担保として、甲に抵当権を設定する旨の契約を締結した。その後、Cの抵当権設定登記がされ、次いで、AからBへの所有権移転登記がされた。この場合において、Bは、甲の所有権の取得をCに対抗することができない。
3.Aは、Bに対して有する貸金債権αをCに譲渡し、Bに対し、確定日付のある証書によらずに譲渡通知をした。BがCにαの弁済をした後、Aは、αをDに譲渡し、Bに対し、確定日付のある証書により譲渡通知をした。この場合において、Dは、Bに対して、αの弁済を請求することができない。
4.Aは、Bとの間で、建物所有を目的としてA所有の甲土地をBに賃貸する旨の契約を締結し、甲をBに引き渡した。Bは、甲の上に乙建物を建てて所有権保存登記をした。その後、Aは、甲をCに譲渡し、Cへの所有権移転登記を済ませた。この場合において、Bは、甲の借地権をCに対抗することができない。
正解:3
〔講評〕
民法ではさまざまな箇所で「対抗」という言葉が出てきますが、それについて横断的に問う問題でした。選択肢3が正しいことを述べており正解となります。AのBに対する債権が、CとDに二重譲渡されており、Dが第三者対抗要件を備えているのに対して、Cは債務者対抗要件しか備えていないということだけみると、DはCに優先し、DがBに対する弁済を要求できることになりそうにみえます。そのせいか、正答率は3割を少し超えるくらいでした。しかし、Dへの譲渡について対抗要件が具備される前に有効な弁済が行われたことでαは消滅しており、Bは、この事実をDに対抗することができます(民法468条1項)。このため、DはBに対して弁済の請求をすることができません。
むしろ、誤答である選択肢2を選んだ受験生の方がわずかばかり多くいました。Bの所有権取得とCの抵当権取得とでは、後者の方が先に対抗要件(登記)を備えているのですが、不動産に抵当権が設定されていることは、当該不動産の所有権の移転を妨げるものではありません。Bは、抵当権の負担付きの所有権を取得したことになり、このこと自体はCに対して対抗することができるため、選択肢2は、誤った内容を述べていることになります。
なお、選択肢1については最判昭33・8・28民集12・12・1936を、選択肢4については借地借家法10条1項を参照してください。
問6
求償に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。
1.Aは、Bに対して金銭債務を負っており、Cは、この債務を担保するため、その所有する土地に抵当権を設定した。この場合において、Cがこの債務を弁済したときは、Cは、Aに対して求償することができる。
2.AおよびBは、Cに対して連帯して金銭債務を負っていた。AがCからこの債務の免除を受けた後に、BがCにこの債務の弁済をしたときは、Bは、Aに対して求償することができる。
3.Aは、Bに対して100万円の金銭債務を負っており、Cは、Aから委託を受けないでこの債務を保証した。その後、Cは、この保証債務を履行した。その当時、Aは、Bに対して100万円の貸金債権を有しており、その弁済期が到来していた。この場合において、Cは、Aに対して求償することができない。
4.運送会社Aに雇用されたBは、Aの事業の執行としてトラックを運転していたところ、トラックをCに衝突させてCを負傷させる事故を起こした。Aは、この事故によってCが被った損害について、使用者責任に基づきCに賠償金を支払った。この場合において、Aは、Bに対して求償することができない。
正解:4
〔講評〕
これも民法のさまざまな箇所に登場する「求償」について、横断的に問う問題です。正解となるのは選択肢4ですが、これは民法715条「使用者……から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」という規定の内容をそのまま問うものであり、また、実際に事故を起こしたBに負担を負わせることは不合理なことではありませんから、正答率が4割弱にとどまったことは少し残念な結果でした。判例としては、損害の公平な分担という見地から、使用者の求償額を制限する判例(最判昭51・7・8民集30・7・689)や被用者から使用者へのいわゆる逆求償を認める判例(最判令2・2・28民集74・2・106)が有名であり、使用者からの求償ができないという誤ったイメージを抱いている受験生がいるのではないかと、少し懸念をもっています。
なお選択肢1は民法372条が準用する民法351条が、選択肢2は民法445条が、選択肢3は民法462条1項が準用する459条の2第1項前段がそれぞれ定めています。各制度において基本的な規定ですので、この機会にぜひ確認をしてください。