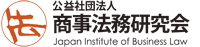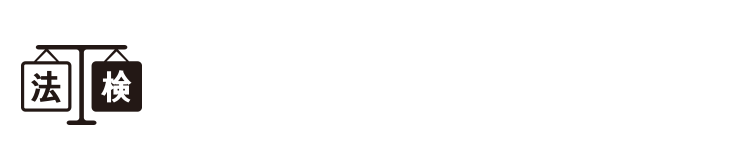法学入門 憲法 民法 刑法 →スタンダード〈中級〉コース講評ページ
【法学入門】
問1
正義の観念について述べた以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.配分的正義は、「等しきものは等しく、等しからざるものは等しからざるように取り扱え」という定式にまとめられ、一定の要件を満たした場合に所定の効果を発生させるという法的思考の様式は、配分的正義の実現に資する。
2.「各人にその責任に応じて」刑罰を科すこと、「各人にその業績に応じて」報酬を与えることは、いずれも自然的正義の一局面である。
3.法適用の手続において、一般的な法規範をそのまま適用した際に個別の事例で生じてしまう不都合を回避するため、法規範の補正を行うのが、衡平である。
4.実質的正義は、判断の内容的正当性を直接に要請するのではなく、判断に至るまでの適正な手続を要請するものであり、そうした手続の遵守に、判断の正しさの根拠を求める。
正解:3
〔講評〕
本問は、法の中核的な価値とされる正義について、基本的事項を問う問題です。正解は肢3で、事案に対して判断を下す裁判所が、実定法のルールをそのまま適用せずに、例外的なルールを立てるなどする場合が、衡平の実践にあたります。肢1は「配分的正義」ではなく「形式的正義」についての、肢2は「自然的正義」ではなく「実質的正義」(の一局面である「配分的正義」)についての、さらに肢4は「実質的正義」ではなく「手続的正義」についての、それぞれ適切な説明です。
問9
以下の組織・機構のうち、日本国憲法のなかでその存在が明記されていないものを1つ選びなさい。
1.弾劾裁判所
2.地方公共団体
3.会計検査院
4.内閣法制局
正解:4
〔講評〕
本問は、日本国憲法が定める組織・機構に関する問題です。日本国憲法は、統治機構の構築に関して多くの部分を法律による定めに委ねる一方で、一部については憲法の条文内でその存在を明言しています。肢1の「弾劾裁判所」については憲法64条1項に、肢2の「地方公共団体」については憲法92条~95条に、肢3の「会計検査院」については憲法90条に、それぞれ規定があります。これに対し、「内閣法制局」について定めた日本国憲法の条文はありません。内閣法制局は、「内閣法制局設置法」という法律に基づき、内閣に設置されています。
【憲 法】
問7
憲法29条3項の損失補償に関する以下の記述のうち、判例に照らして、正しいものを1つ選びなさい。
1.憲法29条3項は、国の違法な活動によって生じた財産上の損害だけではなく、適法な活動によって生じた財産上の損失についても、正当な補償を要求している。
2.憲法29条3項の損失補償は、「公共のために用ひる」ことを条件としているため、特定個人を直接の受益者とする私有財産の収用の場合には、補償されない。
3.損失補償規定を欠く法令による財産上の制限が、特定個人に特別の犠牲を強いることになったとしても、当該法令を直ちに憲法29条3項に違反するものと解すべきではない。
4.農地改革における政府の農地買収価格は、通常の市場取引価格と比べると著しく低廉であり「正当な補償」とはいえないが、戦後インフレというきわめて例外的な経済状況を考慮すれば、憲法29条3項に違反するとまではいえない。
正解:3
〔講評〕
本問は、損失補償に関する一般的な知識を問うものでした。ただ、問題集には掲載されていない問題だったということもあり、その意味ではやや発展的な水準の問題だったといえるのかもしれません。これは24.5%という正答率にも表れておりますし、また、誤答の割合も各肢でほぼ均等(25%前後)となっていることにも表れておりました。全体の受験生におけるこのような解答のバラツキは、「鉛筆を転がして解答を記入した場合」と同様の傾向を示しています。ここから推察するに、今回の受験生の多くは、損失補償についてほとんど学習の手が及んでいなかった、あるいは、少なくとも損失補償の判例についてまでは学習の手が及んでいなかった、ということだったのかもしれません。
ただ、今回出題された問題に関連する諸論点はいずれも基礎的なものであり、判例として学習する機会がなかったとしても、基本書・教科書等の記述において解説されている内容のものばかりでした。財産権の学習において、損失補償は財産権制限と並ぶ2大テーマの1つですので、これを機に、損失補償についての学習を十分に深めるとともに、本問の各肢について十分な復習をしていただけると幸いです。
以下に各肢についての解説を記しておきますので、どうぞ参考にしてください。
1.誤り。憲法29条3項は、国や地方公共団体の適法な活動によって生じた私有財産に対する損失について、正当な補償を行うよう要求するものである。国などの違法な活動によって生じた損害についての賠償は、憲法17条の国家賠償請求権の問題であり、より具体的には、国家賠償法の諸規定に従って賠償されることとなる。
2.誤り。憲法29条3項の「公共のために用ひる」は、広く社会公共の利益のために私有財産の収用等を行うことをいい、特に公共事業のためといった限定をつける趣旨ではない。たとえば、農地改革を通じた自作農創設の直接的受益者は私人であったが、これも「公共のため」に行われたと理解されている(農地改革事件:最大判昭28・12・23民集7・13・1523)。
3.正しい。河川附近地制限令事件(最大判昭43・11・27刑集22・12・1402)において、最高裁は、財産上の制限を定める河川附近地制限令4条2号(以下「本件規定」)に損失補償規定がなくても、これはあらゆる場合に損失補償を否定する趣旨とまでは解されず、「別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」と述べたうえで、損失補償規定を欠く本件規定について、「直ちに違憲無効の規定と解すべきではない」と判示している。
4.誤り。前掲・農地改革事件では、田の最高買収価格が敗戦によるインフレ等の当時の経済事情からみて著しく低廉であり、「正当な補償」とはいえないのではないかが争われたが、最高裁は、「正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」と述べ、この観点から、自作農創設特別措置法6条3項の買収対価をもって憲法29条3項の「正当な補償」にあたると判断した。
【民 法】
2024年度法学検定ベーシック<基礎>コース民法の問題について、ここでは,正答率が1番低かった問題8と、2番目に低かった問題10(いずれも問題集には載っていない問題)を取り上げて講評します。
問8
共有に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2.各共有者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
3.各共有者の持分は、相等しいものと推定される。
4.共有者の1人がその持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
正解:2
〔講評〕
正解となる選択肢2は、民法249条3項が共有者の注意義務を「善良な管理者の注意」と定めていることに反しており、誤りということになります。この選択肢を選び取ることができた受験生は2割弱にとどまりました。選択肢1を選んだ受験生も同じく2割弱、選択肢3を選んだ受験生が約38%、選択肢4を選んだ受験生が約25%ということで、誤答の方が圧倒的に多いという結果になってしまいました。
共有は、物権法・所有権法のなかでもややわかりにくい分野かもしれません。しかし、普段から、「自分の共同所有者の一員だが、自分だけの物ではない」という共有のイメージを思い浮かべながら六法を参照して勉強していれば、誤答となる選択肢を選ばないですんだのではないでしょうか。
なお、選択肢3を選んだ受験生が最も多かったことについては、もしかしたら、「共有の場合には、持分割合は、いろいろなケースがある=相等しいわけではない」という理解から、この選択肢を選んだのかもしれません。もちろんその理解は正しいのですが、ここで問われているのは、その持分割合がわからないときにはたらく「推定」規定です。このような、法律用語一般に関する知識、それも踏まえた条文の機能の理解(どんな場面ではたらくか)についても、普段の学習から身につけていくことが重要です。
問10
債務不履行による損害賠償に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.債務者が債務不履行による損害賠償責任を負うときでも、特別の事情によって生じた損害については、賠償の範囲に含まれない。
2.契約の当事者は、債務不履行が生じた場合における損害賠償の方法について、金銭以外のものを損害賠償にあてることを合意することができる。
3.金銭債務に不履行が生じたときは、債権者は、損害の証明をしなくても、法定利率による損害賠償を請求することができる。
4.契約の当事者は、債務不履行が生じたときに支払うべき損害賠償の額をあらかじめ合意することができる。
正解:1
〔講評〕
正解となる選択肢1は、民法416条2項が「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と定めていることに反しており、誤りということになります。正答率はちょうど3分の1でした。
この問題については、選択肢3を選んだ受験生が半数弱に達していました。選択肢3は、民法419条1項本文「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める」と同条2項「前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない」の内容を問うもので正しい内容を述べています。ただ、受験生の中には、同条1項ただし書「ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による」を想起して、「法定利率ではなく約定利率のはずだ」と思い、この選択肢を誤りと判断したのかもしれません。しかし、このただし書の規定があったとしても、少なくとも法定利率による損害賠償をとることができる点は変わりませんので(債権者は、約定利率が高いということの証明を加えることで、より有利な約定利率による損害賠償をとることができる)、選択肢3が誤りであるということにはなりません。
【刑 法】
問10
以下の記述のうち、判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。
1.刑法217条の罪は、老年のために扶助を必要とする者を遺棄することによって直ちに成立し、その成立のために、現実にその者の生命・身体に対する危険を発生させることは必要ない。
2.刑法218条にいう「遺棄」には、単なる置去りも含まれる。
3.刑法218条は、「生存に必要な保護」行為として、幼年者について、たとえば、その親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等全般を行うことを刑法上の義務として求めている。
4.産婦人科医師が、妊婦の依頼を受けて行った堕胎により出生した未熟児に、設備の整った病院の医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのような医療を受けさせるための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置したまま、措置を何らとらなかった結果、同児を死亡させた場合、刑法219条の罪が成立する。
〔参照条文〕刑法
(遺棄)
第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
正解:3
〔講評〕
本問は、遺棄の罪に関するものである。受験者の解答は分かれたが、肢1、2、4は正しい。本問の正解、すなわち、判例に照らして誤っているものは、肢3である。
遺棄罪は、抽象的危険犯であると解され、客体を遺棄することによって直ちに成立するから、肢1は正しい。保護責任者遺棄罪にいう「遺棄」には、単なる置去りも含まれるから、肢2は正しい。肢4の場合については、堕胎をした医師が、なお生育する可能性があると医師が認識した未熟児に医療を受けさせるための措置を何らとらなかったことが、刑法218条の罪に当たると解されるから、その結果同児を死亡させたとき、刑法219条の罪が成立する(最決昭63・1・19刑集42・1・1)。よって、肢4は正しい。
近時の判例は、刑法218条について、老年者、幼年者等につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として、その者の「生存に必要な保護」行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味するとし、同条が、肢3にいうような行為全般を行うことを刑法上の義務として求めていることを否定した(最判平30・3・19刑集72・1・1)。よって、肢3は誤りである。