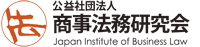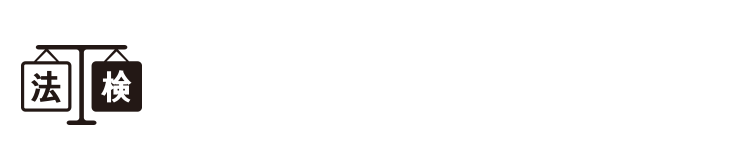法学入門
大学で法律学を学び始めた者が、最低限知っておくべき基礎知識を問う。
憲法
日本国憲法の条文、その通説的な見解、関連する基本判例の趣旨の理解など、憲法の学習にとって必要な基礎知識を問う。
民法
総則と債権法に相対的な重きを置きつつ、物権法(担保物権法は含まない)も含めて、基本的な制度について条文と通説の正確な理解度を問う。家族法や民法典に密接に関連する借地借家法等の特別法に関する初歩的な基礎知識を問うものも含まれる。
刑法
刑法総論の基礎知識を中心に、刑法各論に関しては特に重要な犯罪類型にかかわる基本的事項を問う。
法学一般
大学で法律学をある程度学んだ者として、知っておくべき基礎知識を問う。
憲法
憲法の基礎知識があることを前提にして、憲法上の主要論点にかかわる学説・判例のより深められた理解力、推論して考える力を問う。
民法
民法典全分野における基本的な法制度について、判例を含めて、簡単な事例問題も用いて、正確に理解しているか否かを問う。密接に関連する制度の相互関係を問う問題や特別法(一般法人法、借地借家法、等)に関する基礎的な問題も含み、担保物権法については初歩的な基礎知識を問う問題に限る。
刑法
刑法全般に関する主要なテーマについて、判例・学説の基本的な理解力を問う。総論についてはすべてにわたるが、各論については個人的法益に対する罪(特に財産犯)を中心とし、社会的法益・国家的法益に対する罪からは基本的問題を出題する。
民事訴訟法
総論、裁判所、当事者・代理人、訴えの種類・対象、訴え提起の手続・訴訟の進行、口頭弁論から判決に至る一連の民事訴訟手続に関する全体的な制度の基本的な仕組みと初歩的な法的知識・理解力を問う。多数当事者訴訟、上訴・再審等については、とりあげない。
刑事訴訟法
犯罪の捜査、公訴の提起、公判手続、証拠法、裁判、上訴という刑事手続の流れに沿い、刑事手続の基本原理、制度の基本的な仕組みと初歩的な法解釈上の論点に関する知識・理解力を問う。
商法
会社法に関する基本的な法制度と若干の実務的な内容を中心に、商法総則、商行為法総則の初歩的な内容も範囲とする。企業に関する私法規制の基礎知識と単純な事例を通しての法的理解力を問う。
行政法
広義の行政法総論が主たる出題範囲である。狭義の行政法総論のほか、国家補償法や行政訴訟法についての基礎知識を問う。行政法各論特有の問題は基本的には出題しないが、総論との関係で必要な事項は学習しておくことが望ましい。
基本法総合
基本的には、スタンダード〈中級〉コースの憲法・民法・刑法の出題範囲・内容と同様である。しかし、やや難易度の高い問題や他の法分野との境界領域の問題も出題範囲とするので、憲法・民法・刑法のより深い理解が求められる。
法学基礎論
法哲学、法社会学、比較法、日本法制史、司法制度論、法的思考の基礎から出題する。上級者としては、実定法の知識だけではなく法規範の成り立ちや解釈の基礎についても学習をし、理解を深めてほしい。
憲法
学説については、各説の論拠とその当否を論じ自説を展開できるか、判例については、争点および判決要旨に加え、事案の内容・判決の理論構成・有力な反対意見・学説の論評等を理解しているか、比較憲法については、概括的であれ主要国の憲法史・憲法理論・憲法運用の実際を理解しているかなどが問われる。
民法
担保物権法、親族法・相続法を含む民法典全分野、および、特別法(一般法人法、借地借家法、消費者契約法、利息制限法、製造物責任法、区分所有法、動産・債権譲渡特例法)についても理論上・実務上重要なものは出題範囲に含める。法哲学、法社会学、比較法、日本法制史、司法制度論、法的思考の基礎から出題する。上級者としては、実定法の知識だけではなく法規範の成り立ちや解釈の基礎についても学習をし、理解を深めてほしい。
刑法
刑法典全般に及び、刑法総論については判例・学説の基本的知識および応用力を問う。刑法各論についてはすべての犯罪類型について正確な知識を要求する。
【A群】
民事訴訟法
複雑訴訟、多数当事者訴訟、上訴・再審、特別手続も範囲とし、裁判所法、人事訴訟法、仲裁法、民事調停法、非訟事件手続法等を含む。
刑事訴訟法
刑事訴訟手続の全分野を対象とし、刑事訴訟法・刑事訴訟規則に加え標準的な教科書で扱われる憲法についても出題範囲に含む。標準的な教科書で扱うレベルの学説・理論および基本判例の理解や、基礎的知識を具体的設例等に応用する能力を問う。
商法
会社法、商法総則、商行為法、手形・小切手法の分野から、重要な条文・判例について、制度の趣旨を踏まえて理解しているかを問う。
行政法
広義の行政法総論(国家補償法、および行政争訟法からなる行政救済法分野をも含む)が主な出題範囲となる。また、行政組織法分野の重要問題について出題することがある。スタンダード〈中級〉コース問題集の解説を踏まえた、より応用的・発展的な知識と理解力を問う。
【B群】
労働法
労働基準法、労働組合法、労働契約法などの基本的な法律を中心に、これらに関連する育児・介護休業法、労働契約承継法等についても、最低限の内容を把握していることを前提とする。また労働法は特に判例が重要であり、労働契約や労使関係、労災などにかかる中心的な判例法理の理解も前提となる。
破産法
破産法全般について基本的な理解が得られているかを問う。
経済法
独占禁止法を中心とし、関連法令を含む。民法・刑法その他の法分野でも、独占禁止法の法目的と同様に競争政策を実現する手段として登場する範囲で出題範囲に含める。
知的財産法
特許法と著作権法から各4問、知的財産法の基本的な事項から2問出題する。知的財産法についての基本的な理解を問う。